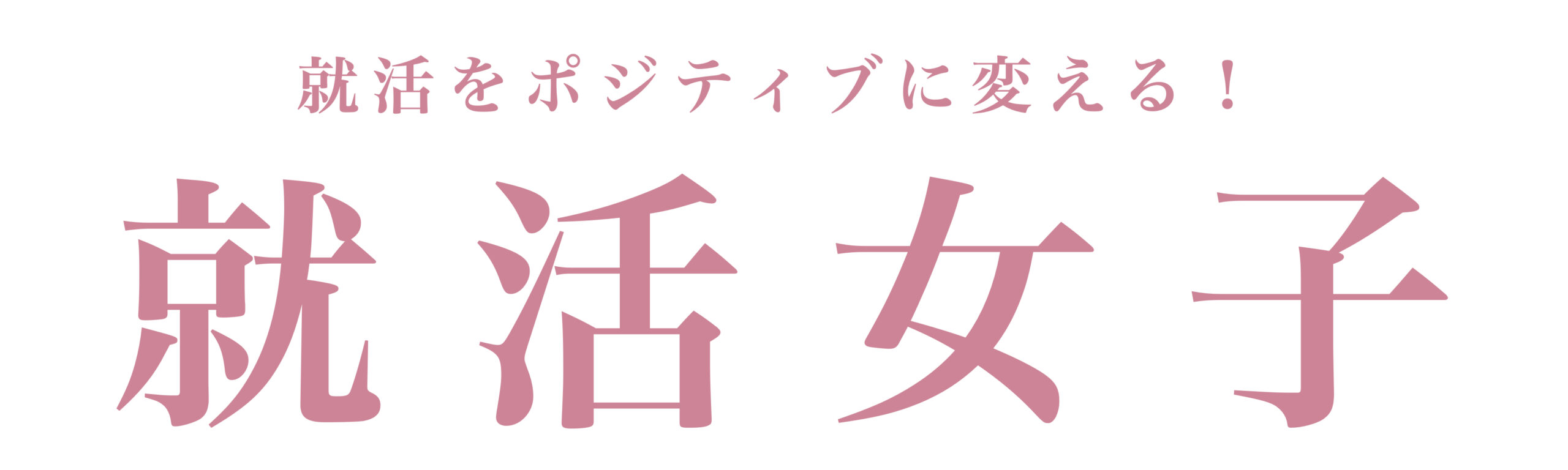はじめに
就活生の皆さんは、公務員志望か民間志望か決まっていますでしょうか?
中には、まだ迷っている方がいらっしゃると思います。
実は、私は地方公務員就活と民間就活を両立させていました!そこで今回は、私の実体験を紹介します!
悩んでいる方が少しでも楽になると嬉しいです!
公務員就活と民間就活について
まずは公務員就活と民間就活の違いについて簡単に説明します!
フロー:筆記試験(日本史や世界史、数的処理など、主に高校で習う科目を指す教養科目と憲法、民法などの専門科目の20科目弱)→面接→内定
スケジュール:大学4年生の春ごろから本選考がスタート。内定を獲得するのは夏~秋。
自治体によっては、筆記試験は教養科目だけを受けさせるところもありますが、それでも科目は多いですし、高校で学んだことは忘れていたので、とにかく勉強が大変でした!大学3年生の5月から大学生協で公務員講座を申し込み、オンラインで勉強していました。毎日最低でも2時間は公務員試験のための勉強にあてていました。特にインターンシップや説明会には参加していませんでした。面接対策も民間就活メインで行っていたため、公務員試験のための対策は行っていませんでした。
フロー:ES→筆記試験(SPIなど)→面接(内定)
スケジュール:一般的には大学4年生の3月以降から本選考を始める企業が多いが、大学3年生の夏以降から早期選考を行う企業も増えている。
民間就活がダメなら公務員になると決めていたため、行きたい業界に絞っていました。複数の企業の会社説明会をはじめとしたイベント、インターンシップに参加しました。ES添削や面接対策はキャリアセンターの方や、就活コミュニティの方にお願いしました。また、YouTubeで面接ロールプレイ動画を視聴しながら一人で練習していました。筆記試験は、参考書を購入し、1日最低1テーマ(集合、確率など)を解いていました。
両立して感じたこと
早くから就活を取り組めば、両立するのは問題ないと感じました。また、公務員試験の数的処理・判断推理とSPIや玉手箱は似ている部分があるため、どちらかを勉強していると、「この数的処理の問題がSPIと似ているから解ける!」などと感じたことがありました。面接対策もやることは同じです。特に民間企業の面接は型にはまった面接の他に雑談式などがありますが、公務員の面接は割と型にはまったかたちであるため、主に民間企業の面接対策をすることで、適応できると感じました。ですが、受けたい自治体が行っている政策はしっかりと勉強し、自分の意見を持っておくことが大切だと思います。
最後に
悩んでいる方はとりあえず両方取り組んでみてもいいと思います!
後から「やっぱり合わないな」と思ったらやめて一本に集中してみてもいいと思います!